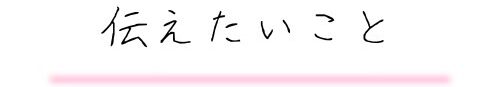今回は一般人の創作したすべらない話を5つ、まとめてお送りします!
スタバ

ラーメン屋でバイトしてたから、とんこつラーメンで数える癖が抜けないんです
「どう言う事ですか?」
今スタバでバイトしているんですが、フラペチーノを頼まれると「とんこつラーメン2杯一丁!」とコーリングしてしまうんです
「なぜ」
フラペチーノがとんこつラーメン2杯分のカロリーだからなんです
「君は、なんでもとんこつラーメンに換算するのかい?」
ええ、どうやら
「困ったな、これは治療法がない」
どうしたらいいんでしょう、とんこつラーメン200杯先生
キー

「面白い話聞きたい?」
別に
「じゃあ話すね」
いいよ、聞きたいくないって
「私の住んでるマンション、昨日から入れないわけ。気まぐれな管理人に勝手に正面エントランスのキーのパスワードの番号をかえたの。だからマンションの住人はマンションに入れなくなった。キー番号を知っているのは管理人だけ。私は住人が住めないマンションに住んでいるの」
は?
「1号室の佐藤さんは持ち前の腕力で壁を登ったって言うし、お隣の山田さんはマンションに入るのを諦めてネカフェで生活している。みんな苦労してるの。でもおかしいと思わない?管理する側が勝手にパスワードを変えるなんて。でもみんな受け入れちゃうのよね。私我慢できなくて管理人とっ捕まえて一体何が目的なのか聞いたのよ。そしたら管理人は言ったの」
気になるな。な、なんて言ったんだ?
「やっぱこの話するのやめるわ」
裸眼視力

彼の名前は木林といった。きばやしではない。きみつという。
彼は何を隠そう、裸眼で視力が2.0あるのだ。
すごい男だろう。
けれど、視力がある代わりにモテないのだ。
残念な男だろう。
そこで彼はメガネを世の中からなくすことを目指して草の根運動を始めた。
メガネがなくなって、遠くまで見える男が自分だけになればモテると考えたのだ。
「メガネがなくなれば俺が世界を制するんだ」
と鼻息荒くした。
具体的にはメガネ屋の株を買って株主総会でメガネ事業撤退を提言したり、メガネの材料を買い占めてメガネを作らせなくしたりした。
その努力のかいもあって、メガネは当時なくなった。
しかし彼はモテなかった。
メガネがなくなると困る人たちが頑張ってコンタクトを
発明したからである。
つまるところ、コンタクトができたきっかけは木林なのだ。
チーズ

チーズって美味しいよね。
「美味しいよね、確かに。白いしなあ」
ヨーグルトも最高だよね。
「最高だよね、美味しいよね。練乳、かけちゃうよね」
トマトも美味しいよね。
「美味しい…かな、まあ、美味しいよね、白くはないけ
ど」
レタスも美味しいよね。
「美味しくはないよね。白くはないし。白いカビが生えて
たら、そこだけいけるよね」
じゃあさ、ホワイトボードは?
「美味しいよね!白いし、もう、一面全部白いもんねえ。
最高だよねえ、ホワイトだよねえ。練乳かけてもいけるよ
ねえ」
ブラック企業は?
「美味しいよね、白い目で見られるもんねえ。ホワイト企
業なら、なお美味しいよね。それ自体が白いんだから」
川越

川越にきていた。
小江戸と言われる浴衣姿が華々しい観光地を抜けて、ディープな川越の「レコードが流れる」ことが売りのカフェに入った。
想像を飛び越えてディープなのだった。面白いつまらなさがある。一般的な「つまらない」も集積すると特別面白くなっていく。
ランジャタイだ。
あげるときりがないけれど、そのカフェに流れる何にも追われないゆったりした時間が好きだった。
お店に入ると、「今起きました」と言わんばかりの寝癖がついた店主が、若干ヨレヨレしながら、今にも消えそうな「いらっしゃいませ」で迎えてくれた。
初対面だけど、この人お昼ご飯ちゃんと食べたのかな、と要らぬ心配をしてしまう。心配するカフェは初めてで新鮮だ。
1階は空席だったが、2階に案内される。
2階も誰もいなかった。貸切だった。
窓際の席に座った。
小学校の校庭が見える。遊具がさびれていて、年季が入っていることがわかる。どんよりとした雲。じめっとした空気。全てがデジタルではなくアナログで、数値に追われていた私は、この世界にもこういう場所はあったんだと安心する。
静かで良い。
座ってしばらく、本を開こうとした時、思い出した。
レコードが流れていない。静かで良いのだけれど。
周りを見渡す。
登ってきた階段の近くに、レコードプレーヤーは今にも落ちそうな形で室内干しの洗濯物のように吊るされていた。
すごい。絶妙な存在感。主役のはずなのに。
寝癖の店主が、階段にギシギシと音を吐かせながら水を運んできた。
レコードのこと、言おうかな、と思ったがやめた。寝起きの店主に余計な負担をかけるわけにはいかない。
りんごジュースを頼んだ。
なかなか運ばれてこない。
15分もかかるりんごジュースが気になった。ミキサーのおとは聴こえなかった。
市販のりんごジュースなら、注ぐのに15分かかることはなかなか想像できない。
いや、しかし一滴一滴丁寧に注いだら15分かかることもあるかもしれない。
15分ほどして運ばれてきたりんごジュースとはいかなるものか。
キンキンに冷えたわけでもなく生暖かく、そして優しい味がした。ここまで主張しないりんごジュースは初めてだった。
紙パックのりんごジュースだった。
美味しかった。
本を読む。
レコードが忘れた頃に「すみません」と申し訳程度の音量でかかった。聴いたことのない民族音楽だった。ジャンガジャンガというリズムが、アンガールズを想起させた。
「このカフェのこだわりって何かあるんですか?」帰り際、なんとなく店主とコミュニケーションを取りたくなり、というか余白しかないこのカフェの秘密を少しでも知りたくなってしまって、きいた。
「強いて言えば、昼はランチ、夜はディナーをやっています」